
2024.07.16
【中外製薬×ことりっぷ】医師監修のもと患者さんQOL向上を願い、はじめての「特定疾患患者さん向け」ガイドブック制作
2023年10月、希少疾患である視神経脊髄炎スペクトラム障害(以下、NMOSD)の患者さん向けに、NMOSDのための薬を開発・販売している中外製薬とタイアップして発行したオリジナルことりっぷガイドブック「やさしい宿と旅」。 専門医の監修や助言を受け、中外製薬が構想をスタートしてから約1年をかけて完成に至りました。 以前ははっきりと原因が分からない、治療が難しい疾患だったNMOSD。NMOSDの治療で重要なのは、再発を予防するための治療です。近年、中外製薬など複数の製薬会社が生物学的製剤という新たな治療薬を開発し、再発予防治療の選択肢が広がっています。症状が緩和したとき「旅」や「おでかけ」が希望になればと、ことりっぷガイドブックは、患者さんはもとより治療にあたる医師からも評価を得ているようです。 今回、ガイドブックの企画をされた中外製薬スペシャリティマーケティング部の通崇夫さんと石見華恵さんにお話をお伺いしてきました。
中外製薬のHPはこちら
治療と向き合い、疾患をコントロールすることで、旅行も視野に

―今回、中外製薬様とタイアップさせていただき、NMOSD疾患をお持ちの方向けに、『やさしい宿と旅』の小冊子を制作させていただきました。なぜ、この冊子を制作しようと思われたのですか。 通さん(以下、通): 私たち中外製薬では、NMOSDの治療薬を開発・販売しております。バイオテクノロジー技術によってつくられた注射薬で、病気の原因となる自己抗体の産生の抑制や、炎症に関わる免疫物質(サイトカイン)の働きを抑制することによって、NMOSDの再発を予防する効果が期待されます。再発を予防することにより、患者さんの障害の進行をおさえ、QOLの維持に繋がると考えています。今まで旅行に行きたくても病気の合併症や再発が怖くて行けなかった方たちにも、安心できる情報があることで旅に出ようと思っていただければと願い、この小冊子を作ろうと思いました。

―NMOSDについて、もう少し教えていただけますか。 通: NMOSDは、間違えて自分の細胞を攻撃してしまう自己免疫疾患のひとつです。主に、脳や脊椎、視神経に炎症が起こり、脊髄に炎症が起きると体の一部が麻痺したり、体幹に強い痛みが出てしまう、といった症状があります。また、視神経に炎症が起こると、視野がかけてしまったり、目の奥に痛みを感じたり、場合によっては失明してしまう方もいらっしゃいます。急に症状が出始め、発症の初期から重症化する方も多く、しっかりと再発を予防する治療を行わないと繰り返すことも特徴です。ですから、患者さんはいつ再発をするのかわからず、不安な日々を過ごしていらっしゃる方も多かったのです。 現在は複数の新薬が開発され、それによって再発予防治療の選択の幅が広がりました。全国で約6500人の患者さんがいるとされており、女性と男性の割合は9:1で、圧倒的に女性の患者さんが多くいらっしゃいます。 患者さんが安心して日々を過ごせたり、暮らしをより彩りあるものにしていただけたらと思い、私たちは薬のこと以外にもライフスタイルに関することなど、積極的な情報発信を行っています。

―今まで、どんな取り組みをされてきましたか 通: 直近では、アーティストのyamaさんとコラボレーションをして疾患啓発の曲を制作しました。曲作りのために、、実際の患者さん達からお話を伺って、それぞれの気持ちや想いを歌詞の中に散りばめてもらいました。また、患者さんのお話を元に10のストーリーとしてまとめ、ショートムービーの制作にも取り組みました。楽曲を作ったり、ショートムービーを作ったことはNMOSDという疾患について多くの方に知ってもらうことが目的のひとつでした。さらに、孤立しがちな患者さんたちに、仲間がいることを知って欲しかったという願いもあります。これらのショートムービーは多くの方の目に触れ、たくさんの方にNMOSDについて知っていただく機会になったと思っています。
NMOSDの患者さんとことりっぷユーザーの層が一致

―ガイドブックを作ることを決められて、なぜ、ことりっぷをお選びいただけたのでしょうか。 石見さん(以下、石見): まずは、見た感じのかわいさが素敵だなと思いました。NMOSDは女性の患者さんが多く、30代後半~50代が好発年齢と言われています。そのため、ことりっぷの読者層とも合致すると思いました。イラストもやさしくて、それが私たちの目指している患者さんに寄り添うという方向性やイメージと合っていると思ったんです。旅がテーマというのも今まで挑戦したことのない新たな切り口で、ことりっぷさんとタイアップをしてNMOSDの患者さん向けガイドブックを作りたい、と社内で相談すると、すぐに賛同してもらえました。
監修医師とも早い段階から協力体制を築きリサーチに活かす

―私たちとしても、初めての医療業界様とのタイアップだったので、どんな冊子をお作りになりたいか、どういった方向けにすればよいかなど、冊子の内容について複数回にわたり打ち合わせをさせていただきました。中外製薬様が目指す冊子はどのようなものでしたか。 石見: 企画からことりっぷのみなさんとご一緒させていただき、どのような内容にするか、どのような症状の患者さんをコアターゲットにするかなど、話し合いを重ねましたね。NMOSDにはさまざまな症状があり、車いすに乗っている方や杖が必要な方、目が見えにくい方など、多岐に渡っており、その症状の重さも様々です。 最初の段階の御社との打ち合わせから監修の先生にも入っていただき、アドバイスをいただいたことで、3者で目指すべき方向性が定められました。その後、ことりっぷのみなさんに宿や観光施設、交通機関へのリサーチを進めてもらううちに、今回は車いすでも介助者と一緒に旅をする方や、杖を使って旅をされる方に向けた冊子にすることがまとまりました。

―いくつかの温泉地を弊社でリサーチして、旅館でしたら温泉の温度や館内の照明具合、誰でもトイレの有無、バリアフリールームや、施設のバリアフリーの有無などを聞き取ったのです。さらに、歩く距離が長くなりすぎないかなどを調べさせていただき、情報共有をいたしました。なぜ、その中から箱根を選ばれたのですか。 石見: バリアフリーで良い宿があったことと、車いすでも無理をせずに観光で回れるコースが組めることでした。首都圏からアクセスが簡便なこともありますね。 でも、私たちとしては場所を紹介することが一番の目的だったわけでなく、別のエリアで宿を探す時の宿選びのポイントなどをお伝えすることが最も重要でした。それをことりっぷさんとも共有し、物件選びにあたってもらえたと思っています。

患者さんが外に出るためのきっかけ作りとなったガイドブック

―今回、監修の先生に加わっていただいたことで、私たちも注意点などがわかりやすく、実際に患者様の立場に沿ったものをお作りできたと思います。 石見: 実は、NMOSDの患者さん向けガイドブックを作るというきっかけを作ってくれたのが、監修の先生だったんです。以前、先生に「患者さん向けに読み物冊子を作るとしたら、どんな情報のものが良いと思いますか」と伺ったときに、「旅行ガイドみたいなものがあるといいね」というアイディアをいただいたのです。そこには、今までのコロナ禍のステイホームで患者さんの心と体の健康が損なわれていないか?という先生の患者さんを心配するお気持ちがありました。外に出てもらうためのきっかけ作りとして、ガイドブックがあればいいなと考えました。
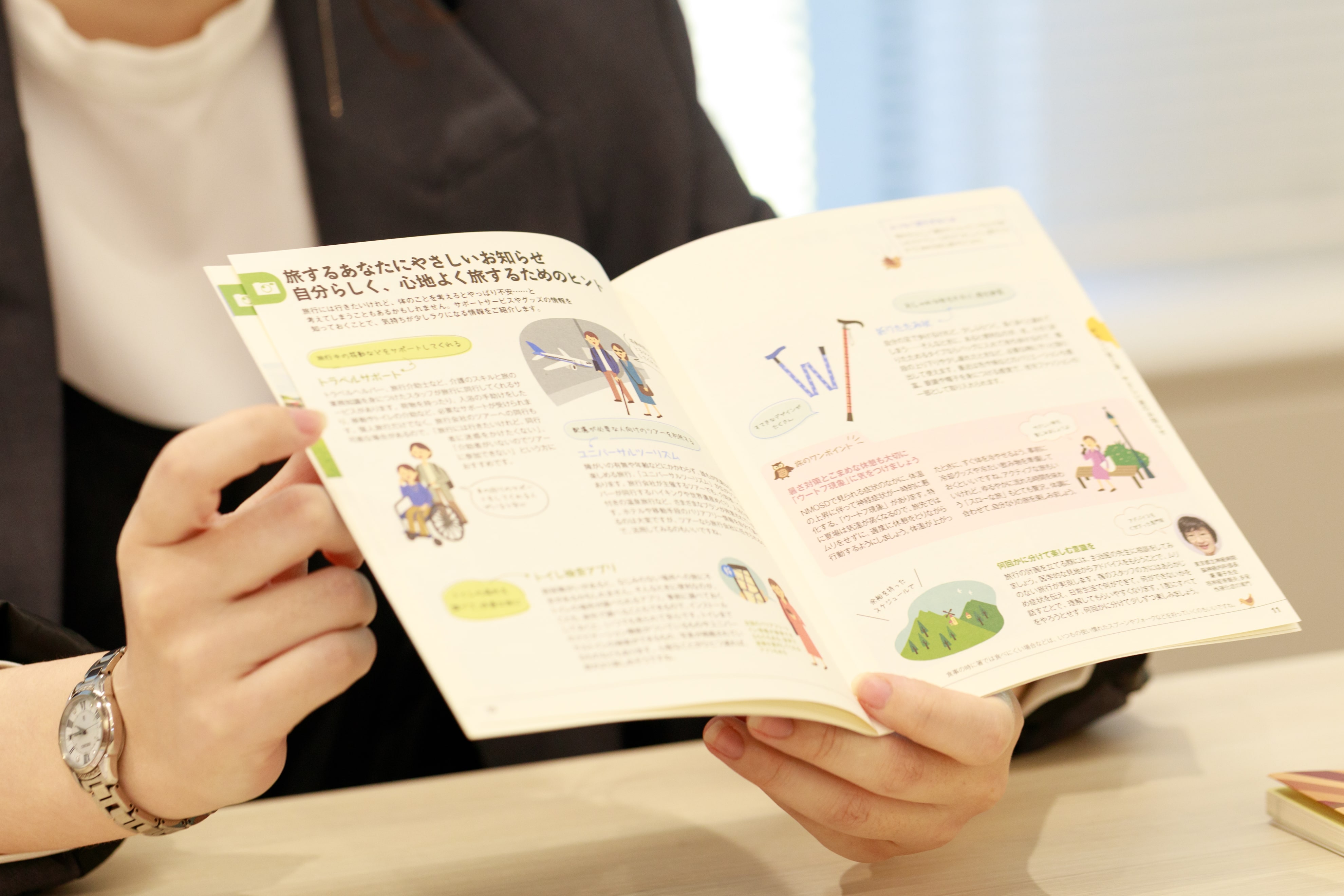
監修医師も取材同行し、現地で直接アドバイス
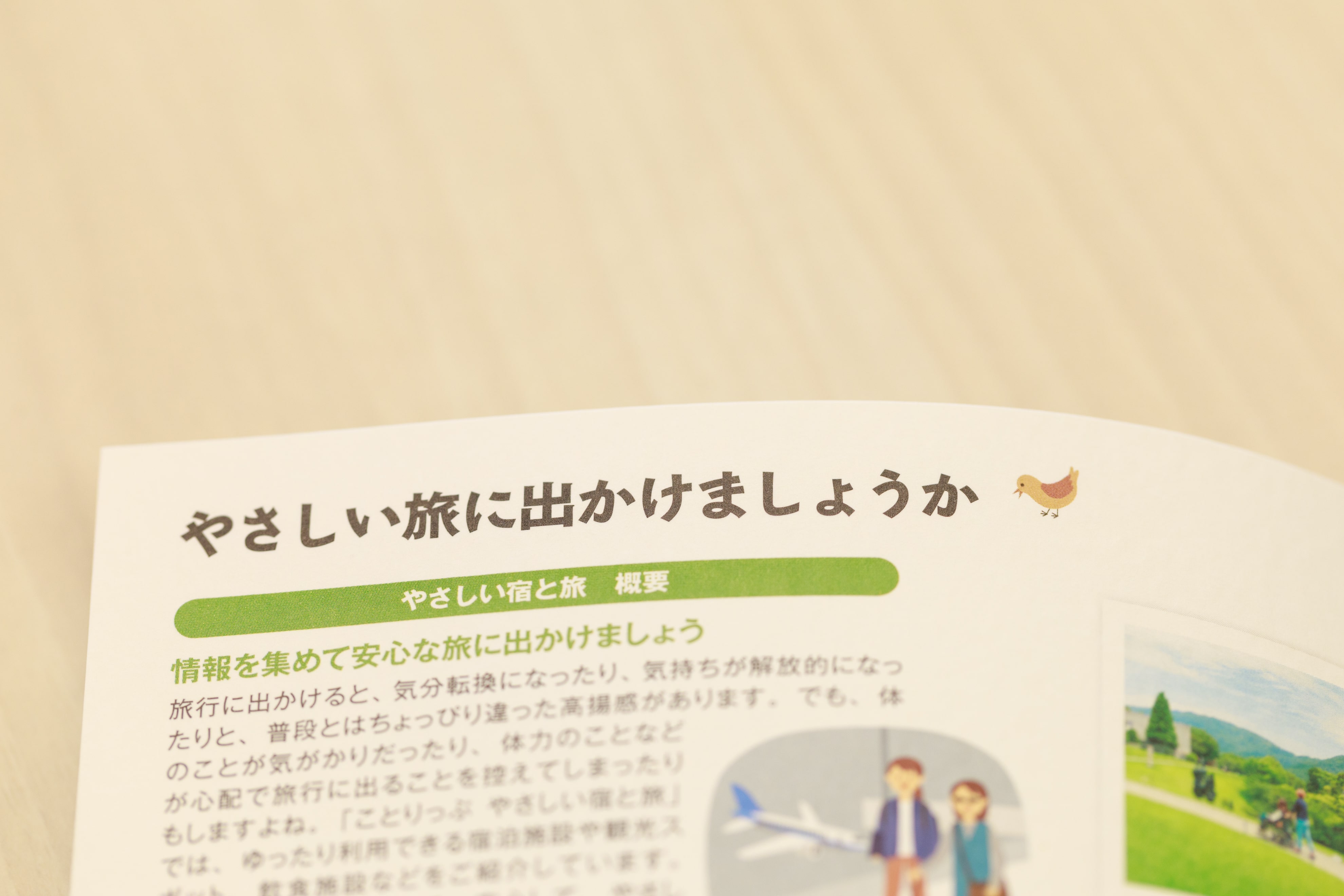
―そうなんですね。実際に取材にも監修の先生を含め、みなさまにも同行いただきましたね。先生には、それぞれのスポットで気をつけるべき点やアドバイスなどを細かくいただき、誌面に反映させることができました。御社のみなさまは取材の際、どのような感想をお持ちになりましたか。 患者さんに一番近く、会話をされる機会も多い先生からのご意見は、どれも貴重なものでした。ことりっぷさんもあらかじめ宿の方にお話しをしていただいていたので、私たちのことも快く迎えていただき、安心しました。実際に自分たちでもルートや施設を視察して、注意点などが明らかになり、これなら身体の不自由な方でも旅行を楽しめそうと具体的なイメージができました。

患者さんが外でも気兼ねなく読める冊子を目指す

―私たちも、箱根の彫刻の森美術館では実際に車いすを押して坂道を登る体験をしてみたり、患者さんの目線に立って冊子づくりをすることを心がけました。表紙に使用している紙はほかの冊子より少し厚めにして、手の動きが不自由な方に少しでも扱いやすいように工夫を重ね、表紙の色みもデザインも明るくポップなものにして、高揚感あるものを目指しました。 石見: 今回の冊子に関して、病気に寄りすぎないと言うのでしょうか…表紙に病気の名前が入っていたり、固いイメージの読み物にするのではなく、病院などに置いてあっても患者さんが「かわいい!」と思って手に取ってもらえるもので、電車の中やカフェなど、家の外でも気軽に読めるものがいいと思っていました。おそらく、製薬業界で初めての取り組みだと思うので、私たちも実現できて満足しています。 通: ことりっぷさんと何度も話し合いを持って、私たちのやりたいカタチを汲み取ってもらったからこそ、思い通りのものが出来上がったと思っていて、とても満足しています。

社内や配布先医療関係者からも高評価

―実際に冊子が完成して、社内での評判はいかがでしたでしょうか。 通: まずは、「ことりっぷとタイアップってすごいね」っていう話がありました。弊社は全国に営業担当者がいるのですが、全国さまざまな場所のご当地版を作って欲しいという要望も複数きています(笑) ―この冊子はどんなところで配布をされましたか。また、社外のみなさま、患者さんからは何かお声が届いていますか。 石見: はい、先ほど申し上げた営業担当者から薬局の薬剤師さんや病院の先生、看護師さんにお渡しして、患者さんに手渡しをしてもらっています。医療関係の方からは、「今までこういったものがなかったので、あると便利ですね」と言っていただいたり、「この冊子をお渡ししながら話のきっかけがつかめた」という声も聞きました。コミュニケーションツールとしても役立っているようで、うれしく思っています。 実際に患者さんからは、「一人では勇気がなくて旅行に出かけにくかったけど、この冊子でトラベルサポートの存在を知り、これなら車いすだけど挑戦してみようかな」とおっしゃっていただいているようです。「読んでいるだけでもワクワクします」など、評判が良く、うれしいです。
動画やWEB版など、今後も取り組みを拡大

―みなさまからの声を伺って、今後の取り組みなど、お話できる範囲で教えてください。 石見: 箱根以外にも、これをモデルケースにして冊子を作れたら良いなと思います。今回の先生はもちろんのこと、ご当地の先生にも参加していただき、ご当地のとっておき情報も載せるなど盛り上がっていくといいですね。この疾患には男性の方もいらっしゃるので、ファッションやアウトドアなど、趣味の括りで冊子を作るのも挑戦してみたいです。今後も常に新しく、患者さんに喜んでいただけるコンテンツを考えたいです。 通: 別の疾患領域にも、この成功体験を横展開していくことは可能だと思っています。また、動画やWEB版なども作ってみたいですし、患者団体様に協力をしてもらい、実際に患者さんに行ってもらった様子を動画で展開するというのもいいですね。 ―私たちも、今後も協力体制が築けるように、情報収集を行っていきます。 本日はありがとうございました。

今回お話をお伺いしたのは、中外製薬にて神経疾患領域のマーケティングを担当している2名 (写真左) 中外製薬 スペシャリティマーケティング部 プロダクトマネジャー 通 崇夫(とおりたかお)さん (写真右) 中外製薬 スペシャリティマーケティング部 石見 華恵(いしみはなえ)さん
浅子百合(クレッシェント)、写真:清水ちえみ