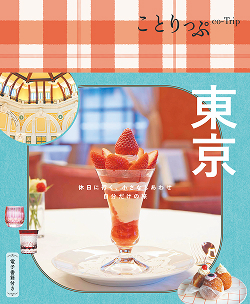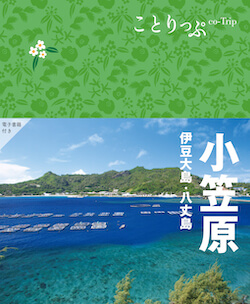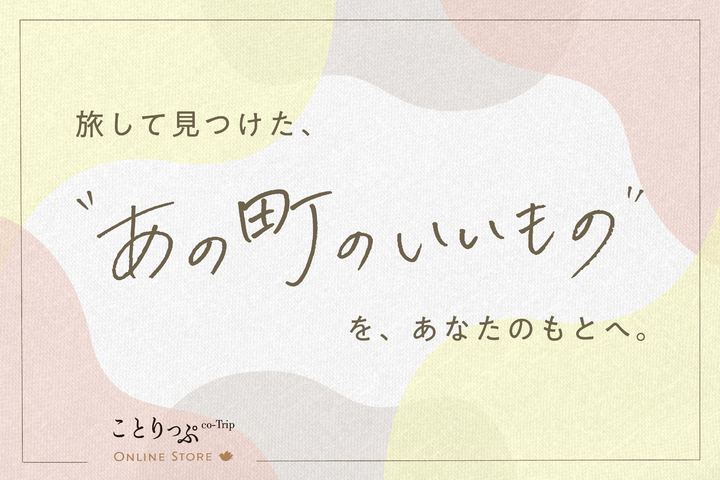2
2025.03.22
創業300余年の桜もちの老舗「長命寺桜もち」で、江戸時代から続く伝統の味を
8代将軍・徳川吉宗が桜の植林を命じた隅田川沿いは、300年以上たった今も桜の名所として有名です。そのほとりに立つ「長命寺桜もち」は、桜並木と同時代に創業した桜もちの老舗。当時から変わらぬ由緒ある手作りの桜もちを味わってみませんか。
隅田川沿いに立つ桜もちの老舗
浮世絵にも描かれる看板娘や隅田堤の風景
今も変わらぬ手作りで愛されるづける名菓
隅田川沿いに立つ桜もちの老舗

「長命寺 桜もち 山本」と書かれた暖簾が目印
季節ごとにさまざまな表情を見せる隅田川。そのほとりに桜もちの老舗「長命寺桜もち」がたたずんでいます。 お店の前の墨堤(ぼくてい)通りは、江戸時代は隅田堤と呼ばれ、8代将軍・徳川吉宗が桜の植林を命じたと伝わる場所。桜は大切に育てられ、300年以上たった今も、春になると見事な桜並木が隅田川沿いを彩ります

隅田川にせり出すように枝を伸ばす桜並木(撮影:市来恭子)
浮世絵にも描かれる看板娘や隅田堤の風景

左/「江戸名所百人美女 長命寺」(東京都立中央図書館) 右/「江戸自慢三十六興 向嶋堤ノ花并ニさくら餅」(国立国会図書館「NDLイメージバンク」https://ndlsearch.ndl.go.jp/imagebank)
「長命寺桜もち」は、吉宗の植林と同時代の1717(享保2)年に、隅田堤沿いに立つ長命寺の門番だった山本新六が、隅田堤の桜の葉を樽で塩漬けにした桜もちを考案し、お寺の門前で売ったのが始まり。以来、約300年もの間、変わらぬ製法で職人がひとつひとつ桜もちを手作りしています。 江戸時代から現在に至るまでロングランの人気を誇る「長命寺桜もち」は、桜の時季にはとくにたくさんの人が目当てに訪れ、長い行列ができるほどです。 現代ではSNSにおいしそうな桜もちの写真がアップされていますが、江戸時代の人気ぶりも浮世絵からうかがうことができます。 初代・新六の孫娘のお豊さんは、歌川国貞の「江戸名所百人美女」の一人として描かれ、猿若町の芝居の題材としても上演されたという看板娘。また、同じく国貞が描いた「江戸自慢三十六興」の「向嶋堤ノ花并ニ(ならびに)さくら餅」では、女性2人が竹かごに入れた桜もちを棒に渡して運んでいる様子が伝わっています。
今も変わらぬ手作りで愛されるづける名菓

「召上り」は桜もち1個に煎茶が付いて500円
桜もちというと、もち米を蒸して粗く引いた道明寺粉を使い、食紅でピンク色に染めた関西風もありますが、関東風は真っ白。「長命寺桜もち」も生地は小麦粉と水でシンプルに作った薄皮で、北海道産の小豆を使ったこし餡を優しく包んでいます。 桜もちの香りを決める葉には、西伊豆の松崎町で採れるオオシマザクラの大きな葉がぜいたくに3枚使われ、もっちりとしたなめらかな食感とともに、さわやかな桜の葉の香りがふんわりと鼻をくすぐります。

持ち帰り用は、すぐに食べられる「バラ」1個250円のほか、「箱詰」5個入り1500円~、「篭詰」10個入り3100円~など
1個から購入できる「バラ」や「箱詰」「篭詰」など持ち帰り用のほか、温かい煎茶とセットで店内でいただける「召上り」もあります。「召上り」がお休みになる桜の時季は、「バラ」を買って隅田川の桜を眺めながらいただくのもおすすめです。 最寄り駅は押上駅と曳舟駅で、どちらからも徒歩15分ほど。隅田川沿いのおさんぽのおともに、300年以上愛され続けている老舗の桜もちをぜひご堪能あれ。

店内には緋毛氈のかかった席やテーブル席、小上がりの席が

長命寺桜もち
チョウメイジサクラモチ
ことりっぷ編集部おすすめ
このエリアのホテル
※掲載の内容は、記事公開時点のものです。変更される場合がありますのでご利用の際は事前にご確認ください。
※画像・文章の無断転載、改変などはご遠慮ください。
文:いちきドーナツ 市来恭子 撮影:上浦未来
Writer
いちきドーナツ 市来恭子

東京在住のフリー編集兼ライター。尾道観光大使・群馬県文化審議会委員。すてきな情報をお届け♪
の人気記事