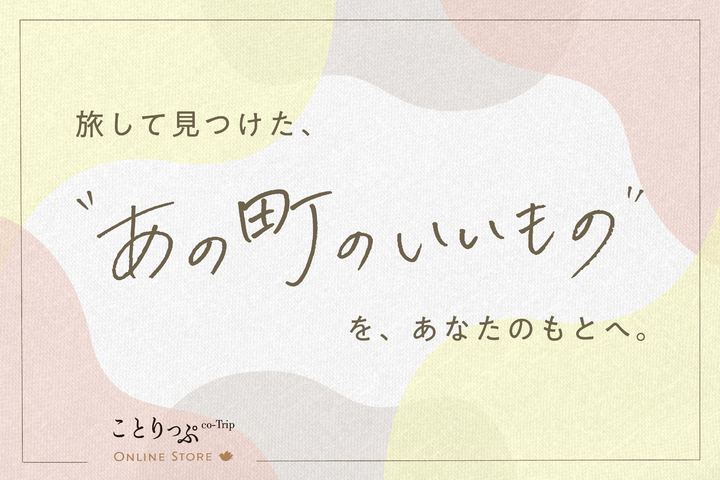41
2015.06.05
【連載・暮らしと、旅と…】与論島、語り継いでいきたい大切なもの
トラベルライター朝比奈千鶴による、暮らしの目線で旅をする本連載。奄美群島をめぐる旅で訪れた、与論島の話は今回で最後です。旅人にとって与論島最大の魅力は、世界を見渡してもトップレベルの美しさを誇る海の青さでしょう。でも、暮らしの目線で旅をしていると、与論ならではの伝統的な布織物や方言、祭りなどの文化が気になります。そこで今回は、「与論民俗村」を訪ねてみることにしました。

鹿児島県・奄美群島の最南端に位置する与論島は、県庁所在地のある鹿児島市内から約560kmも離れています。23㎞南へ行くと、すぐ沖縄本島という限りなく沖縄に近い場所。琉球王朝の時代には、琉球に属していました。そのせいか、薩摩藩や米軍統治以前の400年以上前の史実ではありますが、島には琉球文化の影響が色濃く表れています。沖縄に行ったことがある人ならば、島人が話す言葉のイントネーションや古民家の姿に「沖縄に似ているなあ」と思うかもしれません。 「与論民俗村(以下民俗村)」は、古民家や民具、風習、言葉など与論島の民俗文化を後世に伝えることを目的に、昭和41年4月に菊 千代さんが独力で始めた私設民俗資料館です。 民俗村に到着してまず驚いたのは、民俗村を営む菊さん一家同士が話すと、何を言っているのか全くわからないこと。これまであちこち出かけてきましたが、ここまで単語もわからない、何を話しているか想像すらできない言語は初めてです。与論の方言のことを「ユンヌフトゥバ」といいますが、千代さんは、ユンヌフトゥバをはじめ、民俗文化、歴史などを伝える、島の語り部でもありました。


「昭和34年頃から民具を集め始めていますが、その頃から新しい電化製品や家具が入ってきて、がらっと島の生活は変わったんです。台風のあと、ゴミ捨て場に行くと大事な民具がたくさん捨てられていましたよ」と、現在88歳の千代さんは当時を振り返ります。 「与論は隆起サンゴの島だから大きな山がないでしょう? 木材は稀少なので、親から農業、漁業の道具は全部残しておきなさいと言われ、それを守ってきました。小屋に納めておいた民具が、いつか小学生の社会科の資料になるかもしれない、と思ったのがきっかけですね」。高度成長期に入り、時代や物の価値観が変わろうとも、千代さんは民具を保管し続けました。それは、民俗村には島人の歩みを残して後世に伝えようという目的があったからです。だから、菊さん一家は、いにしえの島人の精神そのものでもある言葉「ユンヌフトゥバ」を日常的に使っているのです。


「村の案内をしましょうね」と、千代さんの息子、民俗村村長の秀史(ひでのり)さんに声をかけられ、一緒に村内を歩いてみました。入ってすぐのところにある茅葺き屋根の家には、機織り機等の民具が置いてあります。 秀史さんは村内にあるビロウの葉っぱで柄杓を作り、丸まった葉っぱで水をすくうふりをしました。こんなふうに幼い頃から島にある植物を活用し、暮らしの中で利用していたそうです。 敷地内には赤瓦屋根の民家を復元して展示していますが、菊さん一家は、実際にそこで寝泊まりしています。村内は展示として見せるだけではなく、今も使われている“暮らしの場”でもありました。 「ほら、この植物を見てください。バナナみたいでしょう? この茎から繊維をとって着物に仕立てるんですよ」と秀史さんが指差した植物は、沖縄で見たことがある糸芭蕉でした。糸芭蕉から作る芭蕉布は、沖縄と同じく与論島でも伝統的な布織物です。布に織り上げるまでにかなりの日数のかかる芭蕉布は、現代においてかなりの高級品といわれています。東京で売られている千代さんの織った反物は1反100万円以上もするのだとか。

「そうはいっても、この布を織るのにどれだけの労力がかかるかということを想像してみてください。糸芭蕉から繊維をとりだしていくところから、糸にして布に織り上げるまでの全行程をひとりでするのですから、日当計算してみると1日いくらにもならないんですよ」と秀史さんの奥様、友子さんはいいます。友子さんは千代さんの後継者で、菊家の女性ふたりが与論島で最後の芭蕉布の作り手となっています。 かつては、島の女性のほとんどが日常着として作っていた芭蕉布ですが、その工程の大変さに島の産業にはなりませんでした。高度成長期にはほとんどの織り手が絹織物、大島紬の織り工になりました。当時、大島紬は全国的に売れに売れた時代で、生産に携わる工賃はとても高く、織り工の子どもたちは大島紬のお陰で本土の大学へ行けたといわれているくらいです。 大島紬は蚕のはく絹糸で作る絹織物でハレの着物だとしたら、芭蕉布は身近な植物繊維からなる暮らしの着物。いわばケの着物です。だから、産業としては成り立ちにくく、着るも作るも、暮らしのなかに溶け込んでいました。

民俗村で出会ったガイドの大山文子さんは79歳。少女時代には芭蕉布の着物を織っていたといいます。「一年に一度、旧暦の8月15日に琴平神社で催される十五夜踊りのときは、他の人が織った芭蕉布の柄を見る絶好の機会でした。それぞれ工夫を凝らして織った晴れ着を着てきたので、品評会のようでしたよ。絣(かすり)の模様、色などとても勉強になりました。同時に、男女の出会いの場でもあったから、みんな張り切っていましたね」。 風通しがよく、涼しい芭蕉布の着物は夏祭りの晴れ着にぴったり。1年に1度のお楽しみに向けて機を織る、与論島の乙女たちの姿が頭に浮かびました。 私も芭蕉布を織ってみようと、民俗村の体験メニューにある芭蕉布コースター作り体験を申し込みました。すぐに機織り機に座れるのかと思いきや、計2時間のコースター作りは、糸をつなぐ作業を1時間かけて行い、あとの1時間で機織り機を使って織ります。 芭蕉布は自分で糸を作らないと織れないのが特徴なので、織ることよりも、糸をつなぐことを体験としては重要視していると千代さんはいいます。 民俗村では、冬の間に糸芭蕉の皮を木灰汁で煮て、竹ばさみでしごいて繊維を取り出します。そして、それをつないでおくこの作業を毎年やっています。

コースター織り体験は、繊維を細く裂いてつなぐところから作業は始まりました。繊維をつないで長い1本の糸を作るのです。結び目が一番小さくて簡単に解けないといわれている機結びをし、それを糸車で撚りをかけて糸として使えるようにします。 「糸つなぎは大変な作業ですが、こうやって出来上がっていくのが楽しいということを体験してもらえたらいいですね」と千代さん。 芭蕉布はパーツを作るまでが大変です。大量生産の織り物は、分業化してしまったため現代は誰もゼロから作れなくなっている、と千代さんは嘆きます。 そういう千代さんは、私が民俗村に入ってきたときから、ずっと手が動いていました。芭蕉布は糸つなぎが一番時間のかかる作業で、春先は時間が空けば糸をつなぐために手を動かすのが習慣になっているそうです。 私も手を動かし、1時間かけてやっと小さなコースターを織るためのヨコ糸に使えるだけの量が完成しました。

糸が完成したので、機織り機へ。タテ糸がセットされた機織り機にヨコ糸を入れて、櫛の歯のような筬(おさ)で手前に糸をカンカンと打ち詰めます。そしてまたヨコ糸を入れて機を動かす……シンプルな織り作業は、他の織物と同じです。 芭蕉布は糸が乾燥しやすいため、霧吹きで糸を湿らせながら、カタンコトンと板を踏んで糸を詰め、足と手を交互に使って自分のリズムで織っていきます。そのリズムがつかめてくるのは10回くらいタテ糸とヨコ糸が交差してから。その頃には、カタンコトンが何とも気持ちが良く聞こえてきます。

「形が出来てくると楽しいでしょう? 織る作業は最後のお楽しみです。芭蕉布の作業は、のんびりでしか出来ませんよね。だから、産業ではなく自家用なんです。専門の織り手はいません。家事や農作業などをしながら暮らしの中で織っていくものだから、慣れた人でも一反織り上げるのに2ヶ月くらいかかりますよ」と友子さん。 「糸芭蕉を育て、大きくなったものから繊維をとって糸を紡ぐことを考えると、一反完成させるのにも1年がかりです。大量生産できないのでお金になりません。だから、島の女性たちは織るのを辞めてしまったんです。だからといって島にある大切な技術がなくなるのは避けたいんですよね」。友子さんは千代さんと一緒に芭蕉布の技術を残す活動をしています。 千代さんが織り上げたという芭蕉布を見せてもらいました。 びっしりと細かい目と、透き通るような繊細さ。バナナのような植物の繊維から出来たとは思えないような滑らかな手触り。時折、手にひっかかる繊維と繊維のつなぎ目が、自然界にある有機的なゆらぎを感じさせます。これが、芭蕉布の手織りたる証拠でもあります。 自然の中から生まれ、どこも無駄にすることがないという材料や芭蕉布の工程のあり方は、芭蕉布を眺めたり触ったりしているだけではわかりません。 けれども、見えないところに隠れている作り手の精神性や素材を育む環境の美しさをちょっぴり想像できるようになったら、ものの価値が少しはわかるようになったといえるのでしょうか。

「技術は暮らしの精神だ」と千代さんはいいます。一見いらないと思えるものでも、昔の民具から学べるものが何かある、とも。 「ここを、本当の村にしたいという夢があります。何でもお金に換算される消費社会、食べきれない、着きれないものまで作ろうとすることに、不思議だと思わないのが私には不思議です。腹八分の感覚を持つことは、旅行でこういう場所に来ないと気づけないでしょうね。たまに都会に行くと、たくさんの歩いている人たちが何に向かって生きているのかと思うことがあります。会社の業績をあげるために働く、ということは、いったい何に向かっているんでしょうか?」と秀史さんは疑問を投げかけました。 経済を中心に成り立っている社会に暮らしているだけに耳に痛い言葉です。旅に出る理由として、仕事と暮らしの中で生じるストレスを、非日常空間で解消したい、もしくはチューニングしたいという思いもあるため、旅先でこんな言葉に出会うことは、自分の根本に向かうよい機会かもしれません。 ちなみに、菊さん一家は決して現代の暮らしや経済に背を向けているわけではありません。インターネットや携帯電話を使い、車に乗り、飛行機で出張もします。民俗村も維持をするために入場料をもらっています。 お子さんは本土で民俗学の勉強をしており、将来は民俗村を一緒に営んで行く予定だと秀史さんはいいます。現代の生活様式も持ち合わせながら、島の風土に寄り添った先人の智慧をつないでいくことを菊家は大切にしています。

これから、梅雨の季節に入り、千代さんも友子さんも本格的に織りの作業に入ります。 帰り際に、「来てくださってトゥートゥガナシ(ありがとう)」と菊さん一家が深々と頭を下げて送り出してくれました。 民俗村のゲットウやコロマンソウ、オオタニワタリ、ブーゲンビリア、ハイビスカスなどトロピカルな南国独特の植物が生い茂った中からソテツの道を通り、道路に出ると、ふっといにしえの桃源郷のような世界にタイムトリップをしてきたような気持ちになりました。 古き良き、与論島の暮らしを伝えながら現代を生きる菊さん家族の取り組みは、来年で50周年になるそうです。 旅から帰ってきて、しばらく経ってから自宅でテレビを観ていると、戦後70年の記念番組が流れていました。戦後から高度成長期を経て、バブル期から現代までどんな歩みをしてきたかというシリーズものの第一回目の放送でした。 番組では、わずか70年の間で日本の暮らしががらりと変わった様子と、その背景が描かれていました。戦後の経済復興のため、技術革新をして新しく生まれるものもあれば、それに伴って淘汰されていくものもありました。過去から現代に生きる人たちの努力と選択してきたものの結果、それらが積み重なって現代につながっています。 民俗村は速すぎる時代の流れを踏ん張って持続させてきたのかと思いながら、「なくなるのはあっという間、残すのは大変」と言っていた千代さんの言葉の意味を考えました。島の芭蕉布最後の伝承者となっても決してやめないという強い意志は、どこから来るのでしょうか。「昔の人はものがなかったから、そこにあるもので何でも自分で考えて作り出しましたよ」と千代さんが何度も言っていたこと。そこにヒントがあると思います。 私には「与論民俗村」はこれからの時代の羅針盤は何か、と疑問を投げかけてくる場所に感じました。素朴な南国暮らしのムードのある場所で古き良きものが残っている、という目で見ればそれだけでも訪れる価値はあるのですが、その先にあるメッセージをつかんでくるのもまた、旅の醍醐味というものでしょう。 仕事が分業化したために目の前のことしか考えられなくなること、知らないことにして本当に大事なことをスルーしてしまうこと、その先にある未来。「心地よくなりたい」暮らしの方向性はこれでいいのか、という警鐘を私なりに受け取りました。 さて、次は与論島からフェリーに乗って北上し、隣の島、沖永良部島へ移動します。ここには、どうしても泊まってみたい宿がありました。では、次回もお楽しみに。

与論民俗村
ことりっぷ編集部おすすめ
このエリアのホテル
※掲載の内容は、記事公開時点のものです。変更される場合がありますのでご利用の際は事前にご確認ください。
※画像・文章の無断転載、改変などはご遠慮ください。
朝比奈千鶴
たびレポ
の人気記事
の人気記事