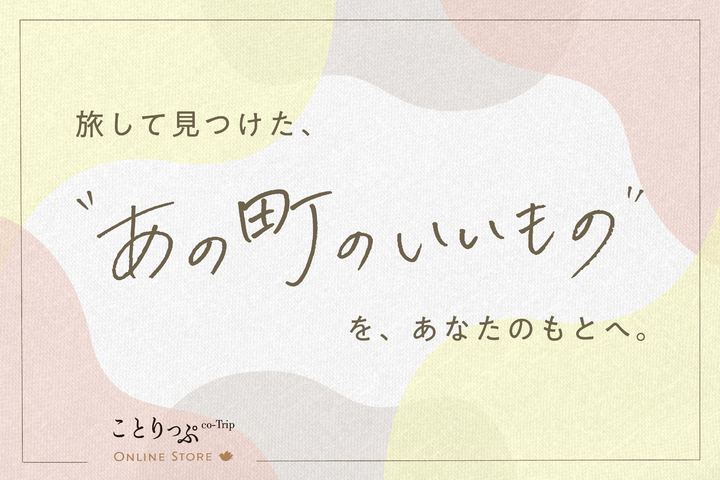![シェフが求めた最上の「RE」。沖縄県本部町のレストランで、1日1組のゲストをもてなすことの意味を知る。[Ristorante RE/沖縄県本部町] by ONESTORY](https://image.co-trip.jp/content/14renewal_images_l/502111/main_image_20201217191559385.jpg)
29
2020.12.18
シェフが求めた最上の「RE」。沖縄県本部町のレストランで、1日1組のゲストをもてなすことの意味を知る。[Ristorante RE/沖縄県本部町] by ONESTORY
「日本に眠る愉しみをもっと。」をコンセプトに47都道府県に潜む「ONE=1ヵ所」の 「ジャパン クリエイティヴ」を特集するメディア「ONESTORY」から沖縄県本部町の「Ristorante RE」を紹介します。

階段を上った先に立つ白亜の建物が『Ristorante RE』。1日1組だけの特別な時間が待っている
「沖縄美ら海水族館」がある町といえば、ピンとくる人もいるのではないでしょうか。那覇空港から車で1時間30分ほど、沖縄本島の北部から東シナ海に突き出した半島にある沖縄県本部町(もとぶちょう)。全国から観光客が訪れる町ではありますが、その一方で今なお古き良き沖縄の暮らしが息づくのどかなエリアでもあります。今回『ONESTORY』取材班が訪れた『Ristorante RE』は、その本部町の北部、具志堅地区の高台にありました。途中、道標となる案内板もなく、国道505号線から脇道に入り、分かれ道を進んでいくと、白亜の建物の前でシェフの三沢 賢(まさる)氏が手をふって出迎えてくれました。

ギラついていたという30代前半までが嘘のよう。今は良い意味で肩の力を抜いてレストランを営む三沢 賢(まさる)氏
那覇から遠く離れた本部という町で1日1組だけをもてなすレストラン。 そう聞けば、どんな料理で訪れる人を驚かせてくれるのか、期待せずにはいられないでしょう。しかし、ここで待っているのは、奇をてらい、訪れた人を驚かせ、未知の食体験を楽しむような、いわゆるコンセプト先行型のガストロノミックな店とは一線を画します。 誤解を恐れずに言えば、決して華やかな店ではありません。味わい、寛ぎ、心を溶かす。 店名に込められたのは、RefreshのREであり、RelaxでREであり、ResortのRE。 本部という町で10年。1日1組のための最上の「RE」を提供し続けてきた店の本質に迫ります。
失敗、そして過ちを経験した若き日の苦い思い出

修業時代の恩師の言葉があり、今の三沢氏がいる。その表情からはかつてのギラつきは感じられない
沖縄本島の北部にある本部町で、1日1組限定で訪れたゲストをもてなす『Ristorante RE』。那覇空港から車で1時間30分ほどの場所で、1日1組のゲストだけに全身全霊を込める。そういうと、どんな変わった料理人が腕を振るう店なのだろうと思うことでしょう。しかし、実際にシェフの三沢 賢(まさる)氏に会うと、そんな一方的なイメージとは全く異なった印象を受けます。穏やかな語り口調で物腰が柔らか。短く刈った髪の毛もあってか、実に落ち着いた雰囲気が漂います。初めて会ったにも関わらず取材班を和ませてくれるような方なのです。 それは、まさに『Ristorante RE』というレストランそのものを表しているかのようでもありました。

店内はテーブル席とカウンター席があるのみ。三沢氏が接客も行い、まさにシェフズテーブルともいうべき空間
三沢氏は、1974年生まれの愛知県出身。高校時代に料理人になることを決心し、卒業後、服部栄養専門学校へ入学しました。在学中は、「鉄人料理人」としても知られる故・澤口知之氏がシェフを務めた『ラ ゴーラ』でアルバイトを始め、卒業後はオープニングスタッフとして、開業したばかりの『ウェスティンホテル東京』に入社したといいます。 ですが、そこで目の当たりにしたのはレストランのイメージとは全く異なる仕事でした。ホテルの調理部門とレストランは似て非なるもの。「考えが甘かったんです。自分の中では面白くなかった」と三沢氏。1年経たずして退職してしまったそうです。 その後の身の振り方を考えた三沢氏は、『ラ ゴーラ』の澤口氏のもとに相談へ。澤口氏の「だったらウチに来い」との言葉に、「行きます!」と二つ返事で答えたそうです。

カウンター席に座った真正面、キッチンの細長い窓からは、沖縄最北端の辺戸岬(へどみさき)が遠くに見える
しかし、そこで三沢氏は、今も悔やんでいる一生の汚点を残してしまうことになります。 澤口氏といえば、業界では知らぬ者がいないほどのシェフですが、それと同時に弟子の指導にも厳しいことで知られた方。多くの弟子がそうだったように、三沢氏も1年足らずで店をやめてしまったといいます。 「やめたというよりも、バックレたんです。今も悔やんでも悔やみきれません。お亡くなりになる前にもう一度お会いしたかった……」と三沢氏は話します。
フレンチのシェフとの出会いが料理人としての三沢氏を変えた

奥様のしずえさんと。別の部屋では奥様がエステティックサロンを経営。『Ristorante RE』の「Relax」の部分を大いに担う
そんな後悔の念を胸に、三沢氏は次なる修業先へ。それが石神井(しゃくじい)公園にあった『ロニオン』でした。 「そこで出会ったのが、『Ostu』の宮根さんと、『ICARO miyamoto』の宮本くん。僕らは同い年なんですが、その3人が決して大きくはない店で同じ時間を過ごせたのは、ある意味で奇跡でした」と三沢氏は言います。 『ロニオン』を離れた後も、時期は異なるものの3人ともイタリアで修業するなど、「いつも同じベクトルを向いていたような気がします」と三沢氏が話すように、同期であり、盟友という関係は変わらず続いたそうです。「切っても切れない縁」と三沢氏は言います。 「イタリア料理のシェフって1974年生まれが本当に多いんです。ふたりだけでなく、修業時代は様々な同い年のシェフと出会って、本当にいろんな刺激を受けました」と三沢氏。

店へ向かう道中に案内板はない。駐車場の前にある看板だけが、ここがレストランであることを教えてくれる
ただ、そうした中で修業時代を過ごした三沢氏は、切磋琢磨し、イタリアで3年間を過ごしたこともあり、当時でいえばまさに「イケイケ」の時。研鑽を重ねたことで力をつけ、自信を増し、自らの実力や技術を誇示したい時期でもありました。料理もいかに自分の色を出すかに躍起になり、当時のシェフ仲間の間で「苦手な食材をいかに美味しく食べさせるかを夜な夜な議論し合っていたこともありました」と言います。 しかし、そんな三沢氏に大きな転機が訪れたのは、イタリアから帰ってきてからのこと。それは意外なレストランでのシェフとの出会いでした。 「調子にのっていた自分の尖った部分を、ドンって上から潰された感じですね。料理の技術云々ではなく、人生の師匠でもあるし、その教えが念頭にあって、今の店の料理と接客があるんです」と三沢氏は話します。

イタリア帰りの三沢氏を変えたのは、銀座にあった『ル・クラージュ』のシェフ・石田和仁氏。なんとイタリアンではなく、フレンチのシェフでした。 「師匠の店では、縁あってイタリアに行く直前に少し時間があったのでアルバイトをしていたことがありました。それがあって、僕がイタリアから帰国すると聞いた師匠が『一緒にやらないか?』と声をかけてくれたんです」と三沢氏は振り返ります。 そこで三沢氏は、料理人として以上のものを石田氏から叩き込まれたのだそうです。 「料理人もお客さんも生産者も、みんな平等じゃないといけない」「おまえが自分を出そうなんて早いんだよ。そんなの50歳を過ぎてからやればいい」。そんな言葉の一つひとつが、今も三沢氏の心の中には刻まれているのです。 もちろん、それらの言葉全てを一度に理解できるはずもありません。 時間をかけて少しずつ、理解していったのでしょう。 「徐々にですが、自分でも丸くなっていくのがわかっていきました。後になって宮本くんと会った時は、『三沢 賢(まさる)じゃなくて、三沢マモルになったね』なんて言われたぐらいでしたから」と三沢氏は話します。
開店休業が続いた5年間。1日1組、誠実なもてなしが徐々に客を呼ぶ

厨房を覗き込むと、コンロには地元の本部牛を使ったハンバーグ。まさに匂いと調理の音までもここではごちそうになる
そんな三沢氏が東京ではなく、沖縄で独立したのは、ほんの軽い気持ちからだといいます。 「お店をやるならどこでやっても当然難しい。であれば、自分が一生いられる場所がいいと思ったんです。小さい頃は転勤族で、子供ができたら同じ思いをさせたくなかったということもあります」と三沢氏。 そこで「レストランを同じ場所で長く続けるには?」と考えた三沢氏。たどりついた答えが、周りに迷惑をかけないことでした。それが1日1組というスタイルだったのです。 ただ、『Ristorante RE』がオープンしたのは、今から10年以上前。SNSが発達し、世界中のどこからでも情報を発信できる時代とは違います。この業界でも「ローカルガストロノミー」という言葉すら誕生していなかった時のことでした。 当然ながら宣伝もしない本部という田舎町のレストランにお客さんが集まるわけがありません。

景色だけではない、お客さんとシェフが一体になってこそこのレストランは更なる魅力を発揮する
事実、独立から5年間は「本当にしんどかった」と三沢氏は振り返ります。 「最初なんかは1年の半分以上が休みでしたからね。ようやく『生活できるかな?』と思えるようになったのも4~5年経ってからで、このスタイルが揺るぎないものになったと思えるのも、ここ2年の話です」と三沢氏。 自らアピールが下手という三沢氏は「本当にお客様が広めてくれたお店」とも言います。 それは閑古鳥が鳴いた日々にも、訪れたお客さんに全身全霊をかけて向き合ってきた結果なのではないでしょうか。 「妻が手伝うこともありますが、基本的に調理も接客も自分ひとり。キッチンの前にテーブルがひとつあるだけの小さなレストランですから、うちは本当にわかりやすい店だと思うんです。お客さんにとって合うか合わないかが、そのまま出る。合う人はリピートしてくれるし、そうでない人は二度と来てくれない。それだけです」と三沢氏は話します。

修業時代の恩師の言葉があり、今の三沢氏がいる。その表情からはかつてのギラつきは感じられない
三沢氏は更にこう続けます。「だからその1組が本当に真剣勝負だし、僕自身がその時間を楽しまないとそれがお客さんにも伝わってしまうんです」。 自ら料理を作り、自ら料理をサーブし、自らお客さんと会話をし、そしてお客さんとの時間を共有し、全身全霊をかけてもてなす。それこそ、「RE」の本質でもあるのです。 三沢氏がイタリア帰りの時のまま、自我を貫き通すままの料理人だったら『Ristorante RE』は、今頃どうなっていたことでしょう。
ことりっぷ編集部おすすめ
このエリアのホテル
※掲載の内容は、記事公開時点のものです。変更される場合がありますのでご利用の際は事前にご確認ください。
※画像・文章の無断転載、改変などはご遠慮ください。
の人気記事